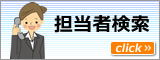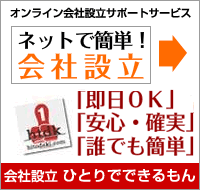マイナンバーを守る、特定個人情報保護委員会とは?
○はじめに
5月24日の参議院本会議で、国民一人一人に番号を割り当て、納税、年金などの情報を一元管理する「共通番号法(マイナンバー法)」が、賛成多数で可決、成立した。投票総数は198、賛成は自民党、民主党など176、反対は共産党、社民党など22だった。
今後は、2015年10月に、国民に対して「通知カード」を郵送して共通番号を通知し、2016年1月からは、希望者に対して顔写真、ICチップ、生年月日、性別、住所が表示された「個人番号カード」を交付するという。年金、納税などの各分野での情報連携が本格的に始まるのは、2017年1月となる見通しとなっている。
共通番号を利用する機関が、通知カードによって本人確認を行う場合は、顔写真入りの書類などと併用し、通知カードに記載された共通番号のみによる本人確認は、基本的にはできないこととなっている。
○特定個人情報保護委員会の設置
これにともない、マイナンバー制度における個人情報の保護を目的とする第三者機関、「特定個人情報保護委員会」が、内閣総理大臣の下に設置される。同委員会の主な業務は、特定個人情報の取り扱いの監視・監督、特定個人情報の取り扱いに関する苦情の処理などとなっている。
マイナンバー制度については、他人の共通番号を勝手に入手し、「なりすまし」による犯罪等に利用されるおそれや、集約された個人情報が外部に漏えいするおそれが指摘されており、それらを踏まえたうえで、システム上の安全管理措置、制度上の保護措置を講じる目的で、同委員会が設置されることとなった。
同委員会は、委員長1名、委員6名で構成されることが決まっているが、実際に実務にあたる職員の数等については、現段階では具体的に決まっていない。5月10日の参議院本会議における甘利社会保障・税一体改革担当大臣の答弁でも、「今後政府内で調整を行い、おおむね数十名程度の事務局体制でスタートした後、効率的、効果的な業務遂行に努めていきたい」という説明にとどまっており、同委員会の機能をじゅうぶんに果たすことができるかどうか、懸念の声もあがっている。
○諸外国における個人情報保護と今後
なお、マイナンバー法に基づき、行政機関、地方公共団体が特定個人情報を保有する場合は、「特定個人情報保護評価」を実施することが義務付けられることとなる。「特定個人情報保護評価」は、特定個人情報ファイルを保有・変更しようとする場合に、プライバシーや特定個人情報に及ぼす影響を事前に評価し、保護のための措置を講じる仕組みで、アメリカ、イギリスなどで実施されている「プライバシー影響評価(PIA)」と同様のものであるという。
また、マイナンバー法では、捜査機関が刑事事件の捜査を行う場合、捜査機関に対して共通番号付き個人情報を提供することができることとなっており、刑事事件の捜査に関わる場合は、特定個人情報保護委員会の権限は及ばないとされている。
アメリカでは、医療、消費者情報など、分野別に第三者機関が設置されており、EU加盟国では、「EUデータ保護指令」と呼ばれる規定に基づき、各加盟国に設置された公的な第三者委員会によって、個人情報の保護を行っている。
○参考リンク
マイナンバー法概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000175483.pdf
EUデータ保護指令仮役(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000196313.pdf
2013年06月01日

最適な税理士が見つかる!
T-SHIEN税理士マッチング
依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。