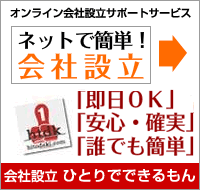[FT]オリンパスの損失隠しは他山の石(社説)
(2011年11月9日付 英フィナンシャル・タイムズ紙)
オリンパスの高山修一社長が、同社の10億ドル超にのぼる不可解な企業買収や手数料の支払いに関し、「適正だ」と株主や世界のメディアに言明したのはわずか11日前のことである。それが8日には一転、20年前の証券投資の損失を穴埋めするための出費であったことを認めた。
■不明瞭な説明が深刻な問題を浮き彫りに
41年間オリンパスに勤めてきた高山氏は、その先の疑問には答えなかった。損失を出した証券投資とはどんなものか。誰がそれを承認したのか。公表するまでこれほど時間がかかったのはなぜか。買収後ただちに評価損を出す企業を買うことが、どのような損失隠しの手法となるのか。もしオリンパス製カメラで撮影した写真が、高山氏の言葉足らずの会見と同じくらい不明瞭だったら、同社ははるか昔に廃業していたことだろう。
だが逆に、オリンパスの過去の買収の経緯がはっきりしないからこそ、同社の抱える深刻な問題を浮き彫りにする効果もある。例えば、「質問をしなければ、裏切られることもない」という社風。これを支えるのは身内を優遇する年功序列の昇進制度だ。しかしその副作用として共謀体質があるのではないか。なぜオリンパスを退職した幹部連が前経営陣の行った不審な取引について(個人的な利益のためではないとされているのに)そこまで沈黙を守ろうとするのか。また、なぜ高山社長や他の役員は英国人のマイケル・ウッドフォード元最高経営責任者(CEO)が疑問を呈したときもっと深く追及しなかったのか。
■資産バブルのつけをいかに処理するか
残念ながら日本の当局はこれまで企業統治(ガバナンス)を向上させる対策に積極的に取り組んでこなかった。企業経営の監視を強化するのに、上場企業に社外取締役の設置を義務づけないのは、その一例。社外取締役が必ずしも万能なわけではないが、取締役会の独立性を高めれば、リスクを減らすことができるのは明白だろう。
また今回の出来事は日本以外の規制当局や企業にとっても多くの教訓がある。特に、収支の悪化やバランスシートの縮小と闘う欧州や米国は参考にすべきだ。オリンパスのスキャンダルは、資産バブルのつけという亡霊を鎮めるのがいかに大変かを如実に示している。バブル崩壊後、日本の企業経営者は降りかかった損失を何とか隠せないかと必死の思いにかられたに違いない。しかし一度出した損失は永遠に「消えて無くなる」ことはない。損失は必ず我が身に返ってくる。結局のところ、一時的に体面が傷ついたとしても、後になって身も心もボロボロになるよりずっと良いのである。
2011年11月09日 日本経済新聞

最適な税理士が見つかる!
T-SHIEN税理士マッチング
依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。